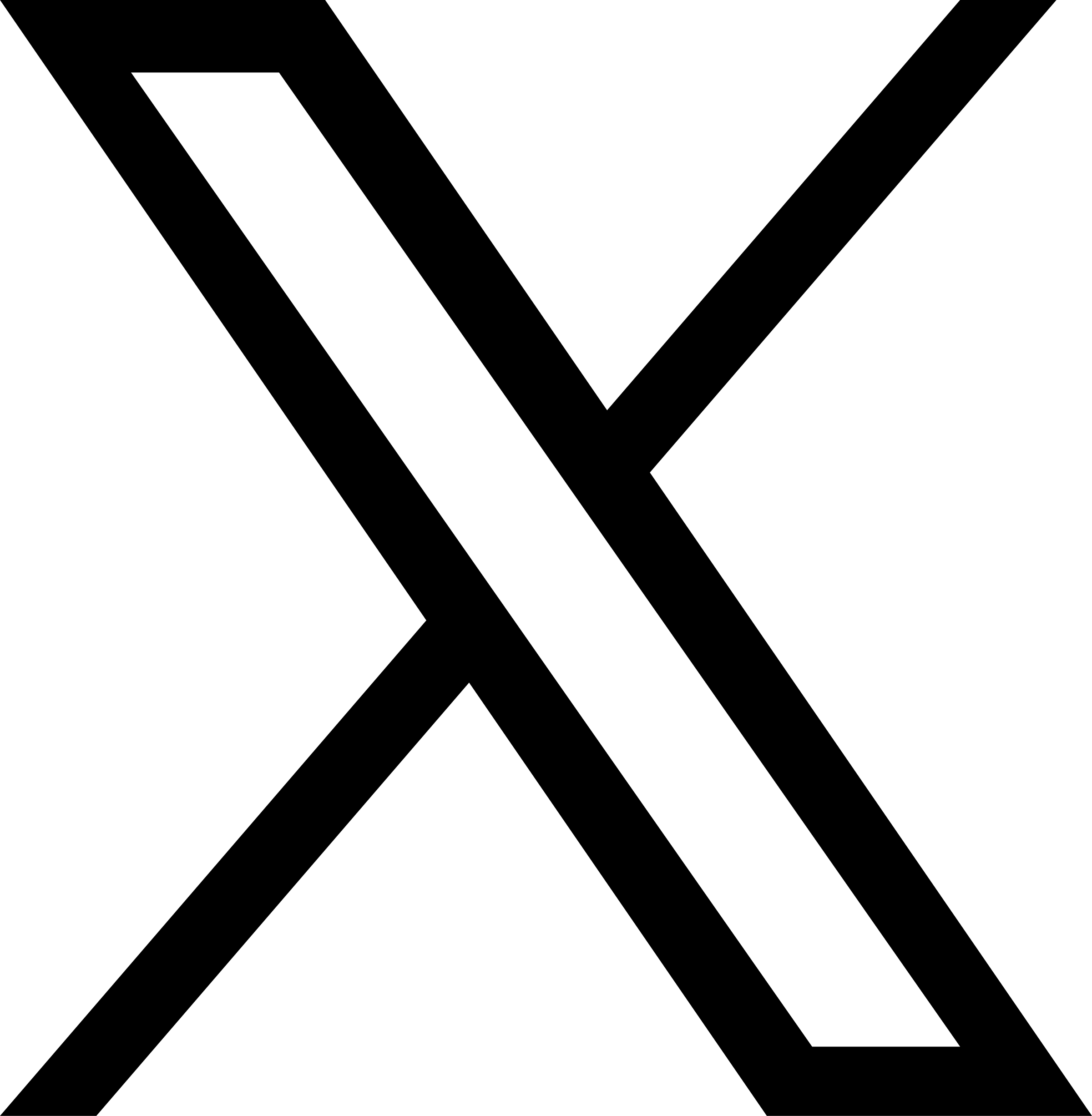このページでは、消費者の皆様からよく寄せられる質問について細胞農業研究機構の見解をお伝えしたいと思います。
最終更新日:2023年6月23日
細胞性食品(いわゆる「培養肉」など)は、世界中で開発が進んでおり、安全性の考え方などについての議論も同時並行で進んでいます。現時点では「これだ」と断定的に言い切れないことが、将来的に新しい研究結果によって見通しが開けたり、もっと正確な表現でお伝えできたと反省したりすることも日々出て参ります。内容は最新の情報を取り入れながらより正しい情報に更新していく予定です。
解答本文は一般財団法人消費科学センター広報誌「消費の道しるべ」2023年4月15日 第704号に記載させていただいた記事「培養肉、改め細胞性食品は新たな食の選択肢になり得るか」の本文を一部更新または抜粋して掲載している箇所がございます
質問の目次
- Q: 「培養肉」とは?
- Q: 「培養肉」は細胞性食品や細胞農業とどう関係するの?
- Q: 細胞培養技術は、家畜で話題になっていた体細胞クローン技術とは違うの?
- Q: 細胞培養と遺伝子組換え技術は異なる技術なの?
- Q: 「培養肉」のメリットは?
- Q: 「培養肉」の課題は?
- Q: 植物性代替肉・大豆ミートと培養肉との違いは?
- Q: 「培養肉」の作り方を詳しく知りたい
- Q: 「培養肉」って食べても大丈夫?
- Q: 知らないうちに流通して食べてしまうのが怖いです。食品表示は適切になされますか?
最新の情報を総合的に鑑みて最も実直な情報の発信を心掛けるため、細胞農業研究機構では、新しい動向などがあった場合、このページを都度更新していく予定です。ただ、最新情報が発表されてから更新までのタイムラグもありますので、最も新しい情報を知りたい団体・組織の方は、ぜひ細胞農業研究機構へお問い合わせください。
定期的にページに来ていただき、皆さまと最新の見解についてすり合わせていきたいと思います。細胞農業研究機構に応えてほしい質問がありましたら、ぜひページ一番下のコメントボックスからリクエストをお願いします。
他にも、下記のようなご質問に今後は答えていきたいと思います!細胞農業研究機構に応えてほしい質問がありましたら、ぜひページ一番下のコメントボックスからリクエストをお願いします。
国際競争(海外技術開発進捗)
- 海外と比べて日本は開発が進んでいるの
おいしさ
- どんな味?どんな食感?
- 高級なお肉と全く同じものが安くできるということ?
社会課題の解決への貢献可能性
- どうして細胞農業が必要なの?実現のために何が足りないの?
- 動物由来の血清や足場材料を使っているなら、結局動物資源に頼っているということでは?
- 大量の電気を使うという点が気になる
- 本当に人口増加に耐えうるたんぱく質供給源になるの?
- 本当に自給率向上に貢献するの?結局アミノ酸やグルコースの原料は輸入しているのでは?
産業
- この産業が普及するといままでの産業はどうなるの?例えば、20年後、30年後の絵姿はどうなるの?